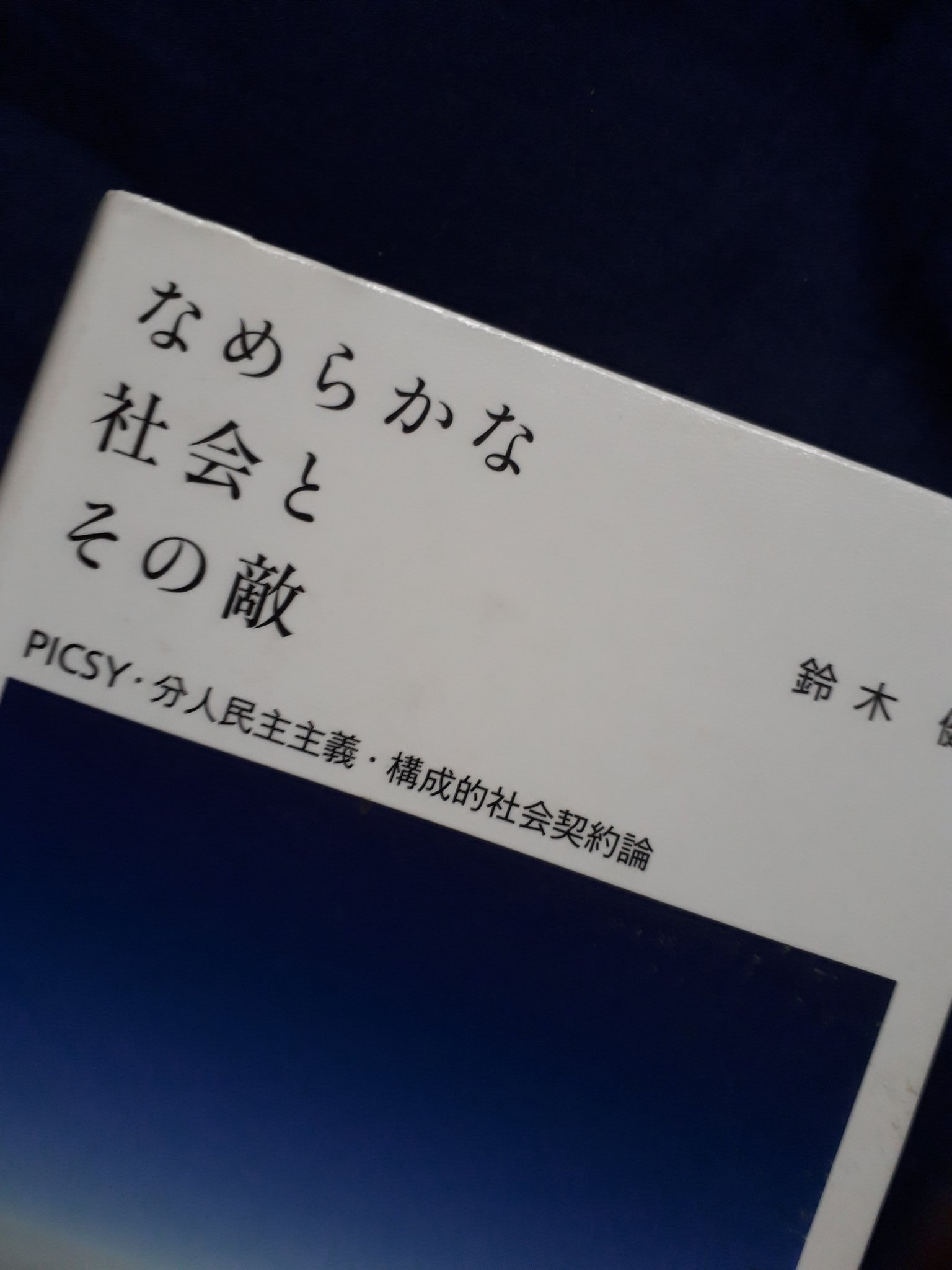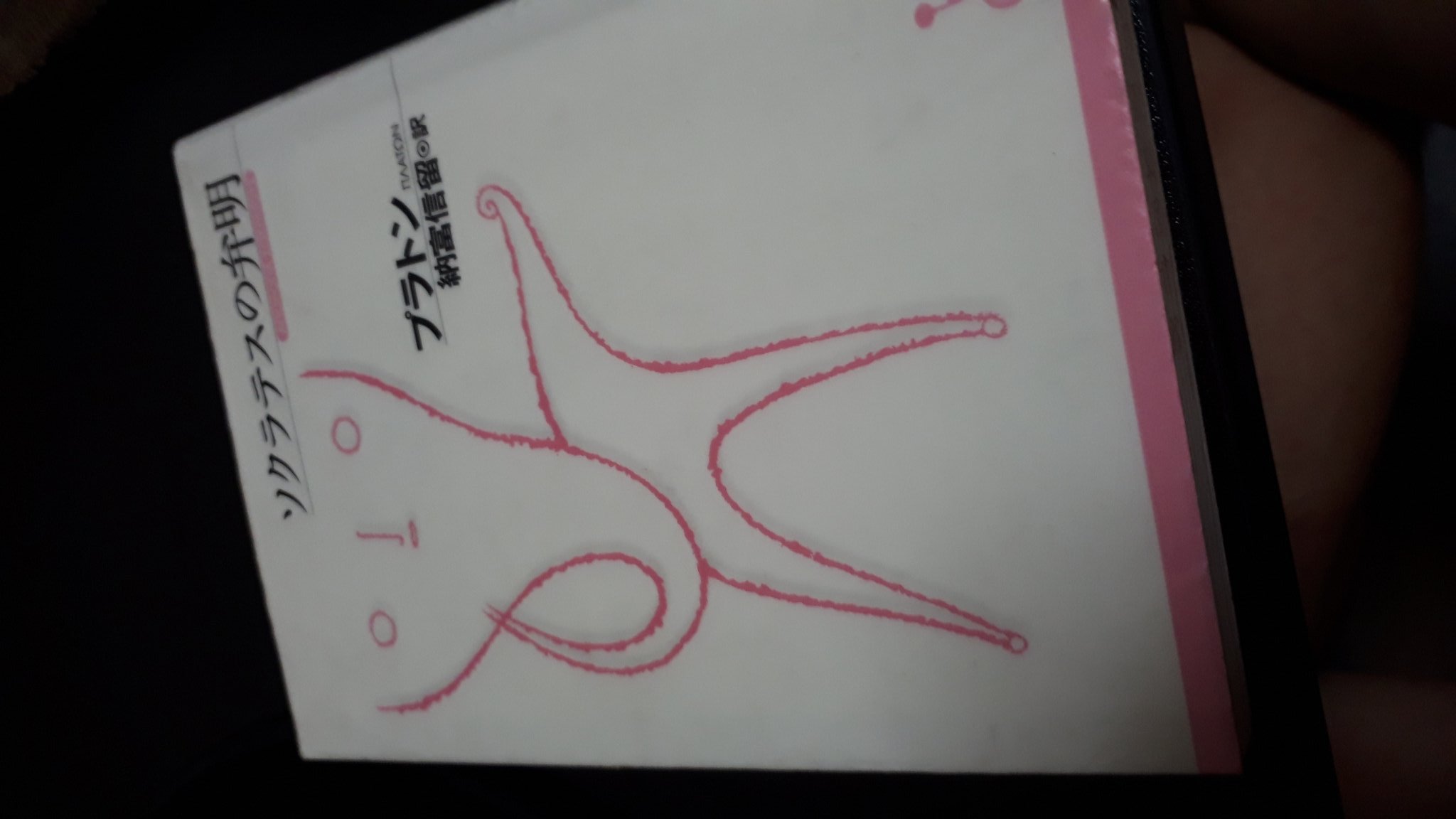最近「ソフィーの世界」を読んだ。きっかけはネットで誰かが読んでよかった本にこれを挙げていたからだ。650ページほどもあるので二の足を踏みそうになるが読んでみるとかなりすらすらと読めた。その理由と内容についての感想を書く。
教科書として使えそうな網羅性とエンタメとして優れた物語
この本の最大の特徴は哲学史をなぞりながら物語が展開しつつ、ちゃんと主人公ソフィーの物語として読めるという点だろう。とくに神話、宗教、科学など哲学と切っても切れないような分野と哲学の関係と歴史が学べるのはこの分野の初心者に嬉しい作りになっている。
ということは哲学に興味がある人間にしか読むことができないかというとそうでもない。主人公ソフィーが不思議な手紙の送り主から次々出される問題を頭の中で試行していく過程は読者から見ても面白い。ソフィーがその年頃の子供にしては、かなり大人びていてなおかつ聞き分けが良すぎる気もするが、それは作者の言いたいことを表現するためには致し方ないと思われる。
物語の中では丁寧に哲学史が語られている。子供にもわかりやすいようにデモクリトスの原子論をレゴブロックに例えたり、ロマン主義的イロニーの話が終わると哲学の先生が誰かに操られたようにイロニーを語りだすのは単純に面白い。
物語の着地点
この物語でソフィーは物語の主人公として作者の思い通りに生きていることを知るが、なんとかしてその物語の作者に一矢報いたいと試行錯誤する。
ソフィーは誕生日会でテーマパーティをしようと思いつき哲学ガーデンパーティを開く。まわりのみんなが爆竹を投げ合ったり、ケーキをテーブルにこぼしバーククーヘンで輪投げをしたり好き勝手やっている。しかし、この場面も哲学の先生にソフィーが教えてもらったシュールリアリズムの話なのだ。
結局、ソフィーたちは生きている人間としてではなく、寿命や死という概念が無い物語のキャラクターとして生きていく。ソフィーの哲学の先生はそれは悲しいことではなく二面性の問題なのだ、と言う。現実に生きる僕たちは生きるということができるがいずれ死ぬ。逆に物語のキャラクターは現実世界に干渉できないかもしれないが死ぬことはない。どう考えるかはその人次第だ。
そう考えると、もしかして歴史に語られている人間もフィクションとしての一面があるのかもしれない。教科書に載るような歴史上の人間たちは、現実世界では人間として死んだが、今もソフィーの物語のように人に伝えられる物語として生きているのだ、というメッセージもあるのかもしれない。考えれば考えるほどこういった風に読めるかもしれない、という作品になっているのでぜひ哲学に興味があっても無くても読んでほしい一冊になっていると感じる。